「お正月飾りはいつから飾るのがいいんだろう?」「毎年飾っているけれど、どういう意味があるの?」とお正月に向けた準備でふと疑問に思うことはありませんか?
今回はお正月飾りの意味、飾りはじめやしまい方など、年末までに知りたいお正月飾りのあれこれをご紹介します。
お正月飾りを飾るのはなぜ?

飾るだけでおめでたい雰囲気を演出してくれるお正月飾りですが、実はちゃんとした意味があります。
鏡餅、しめ飾りなどのお正月飾りは、一年の健康や豊作、家内安全をもたらしてくれる年神様と呼ばれる新年の神様を家に迎え入れるために飾るもの。
しめ縄は悪霊を寄せ付けない結界や厄払いの意味があり、鏡餅は神様へのお供え物となります。
お正月飾りを飾ることは、家に年神様をお迎えするための大切な準備なんです。
しめ飾り・水引飾りについて

しめ飾りは、麻や縄などのしめ縄で作ったお飾り全般のこと。家に年神様をお迎えする準備ができた、という目印になります。地域によって呼び方も種類も様々です。
日本で古くから縁起物として扱われる水引は、引けば引くほど硬く結ばれるという特徴から、「人と人を結びつける」という意味が込められています。
その他には、「魔除け」「未開封の証」という意味合いも。
お飾りはいつまで飾る?しまい方は?

飾りつけは「正月事始め」である12月13日以降に。年末なら12月26~28日、30日がおすすめです。
29日は「二重苦」、31日は「一夜飾り」といわれ、不吉なので避けましょう。
年が明け、「松の内」の期間が明けたら、お正月飾りをしまいます。「どんど焼き」でお焚き上げするのがおすすめですが、難しい場合は分別ごみとして処分しましょう。
塩をかけて清め紙に包んで出すことで、年神様への感謝の気持ちを込めることができます。
【お正月の雑貨市2026】お正月飾りや干支の縁起物など、 午(うま)年に向けて年末までに揃えたいアイテムが大集合
【限定ラッピング】お正月気分高まる迎春ラッピングが登場しました
最終更新日:2025.12.03
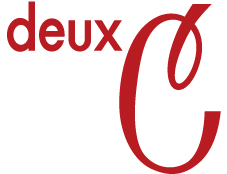





![フラワーベース[プランツベース]パフ](http://deuxc.store/cdn/shop/files/05428001-04.jpg?v=1762854979&width=2262)






